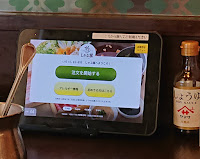私は昔から時代劇のファンです。子どもの頃、家の本棚には池波正太郎、藤沢周平、司馬遼太郎の本がぎっしり並んでいました。通っていた東大阪の小阪中学への通学路には、司馬遼太郎の自宅がありました。ある日、庭の植木に水をやる白髪の老人を見かけ、それが本棚に並ぶあの名著の作者だと知ったときの不思議な気持ちは、今でもよく覚えています。
昨日、録画しておいた映画『侍タイムスリッパー』を観ました。とてもおもしろく、心に残る作品でした。
物語は、現代と江戸を結ぶ“時をかける侍”が軸となって展開します。簡単に言えばタイムスリップものですが、そこには思いのほか深い主題がありました。
それは、「責任の引き受け方」「武士の生きざま」といった、日本人がかつて大切にしていた精神です。今の日本社会に最も欠けているものではないでしょうか。今の政治家を見ているとよくわかりますよね。
この映画には、風情や心情、風習といった、いまや風化しかけている美意識が丁寧に織り込まれていました。一方で、私たちが生きる現代は、何が本物かも分からなくなる「シミュラークル(模像)」の世界。AIやテクノロジーが進化する一方で、私たちの感覚は鈍り、本物と偽物の境界があいまいになってきています。『侍タイムスリッパー』は、そんな世界に対して「本物とは何か」という問いを突きつけているようにも思えました。
高坂新左衛門(山口馬木也)「おれは情けない男だ。」
風見恭一郎(冨家ノリマサ)「おれたちは己の信じる道をせいいっぱい生きた。それでいいじゃないか。」
主演の山口馬木也は、四半世紀前に藤田まこと主演のドラマ『剣客商売』で、息子・大治郎を演じていた俳優です。久しぶりに彼の姿をスクリーンで見て、実にいい役者になったと感じました。年を重ねた分だけ、演技に深みがありました。デビュー直後に藤田まことと『剣客商売』で共演したのが良かったのでしょうか。