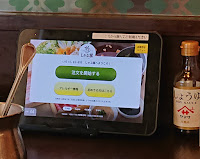先日、わが家で食べたビーフシチュー
昭和三十年代の終わりか、四十年代の初め。場所は福岡市、天神か川端のあたり。正確な場所は記憶の中で少し曖昧ですが、そこに洋画のロードショーを上映する映画館がありました。なぜかその一階(?)には、ちゃんとしたレストランが併設されていて、子どもだった私にはまるで「異世界の入り口」のような場所でした。
映画館で洋画を観る。スクリーンの向こうには、現実にはない世界が広がっていて、その刺激は確実に私の人格形成に影響を与えました。でも、インパクトを受けたのは映画だけではありません。私がそのレストランで出会ったのが、人生初の「ピザ」と「ビーフシチュー」でした。
ピザは、今となってはコンビニでも買える食べ物ですが、当時の私のまわりには、ピザという料理を食べたことのある人間など一人もいませんでした。子どもながらに「これはなんだ?」と圧倒されました。
さらに強烈だったのがビーフシチューです。シチューというからには、牛乳で煮た白いスープのようなものを想像していたのですが、出てきたのはこってりとレンガ色のルウ。その中に、ジャガイモとニンジンがごろりと入っていて、そして、驚くほど大きな牛肉のかたまり。しかも、その肉が、箸でも崩れるほどに柔らかかった。これが“牛肉”なのかと、言葉を失いました。
もうひとつ忘れられないのが、佐世保で食べたハンバーガーです。食べたのは1964年11月、米原子力潜水艦「シードラゴン」が佐世保に寄港したときのこと。当時、核を積んだ原潜の寄港は社会問題となっており、全国で反対運動が起きていました。そんな中、父がなぜか「原潜を見に行こう」と言い出して、福岡から佐世保まで車で連れて行かれました。
昼時に立ち寄ったのが、アメリカ海兵隊相手に営業しているバーでした。昼間だけランチ営業をしていたそのバーのカウンターで、父と並んで出されたハンバーガーにかぶりついた記憶が、いまも鮮明に残っています。パンにはさまれていたのは、肉のパティとスライスオニオンだけという、実にシンプルなものでしたが、それがとにかく旨かった。ポパイの漫画に出てくるウインピーが手にしていた“謎の食べ物”が、ようやく目の前に実体をもって現れた瞬間でした。
そしてもう一つ、福岡スポーツセンターのプールの帰りに友人と食べた町中華のラーメン。お金がなかった私たちは、一杯のラーメンを二人で分けて食べました。今でこそ「豚骨ラーメン」として知られていますが、当時は単に“ラーメン”と呼んでいた気がします。スープは白濁していて、上にはきくらげと紅ショウガがのっていました。器から漂う独特の香りと、どこかクセのある味。でも、それが妙にうまかった。どこか知らない町のにおいがしたのです。
私は4歳から14歳までの10年間を福岡で過ごしました。だから、人生で初めて食べた「外の味」はほとんどがこの町での出来事です。ピザも、ビーフシチューも、ハンバーガーも、ラーメンも。今となっては定番中の定番ですが、あの頃の私は、それらに触れるたびに、世界の広さを体感していたのだと思います。
子どもの頃に「本物の味」に出会っておくことは、とても大切なことです。
それは単なる味覚の話ではありません。社会に出て、一流の人たちとともに働く中で痛感するのは、「本物を知っているかどうか」が、その人の判断力や直感に大きく影響するということです。本物を知っていれば、ニセモノに対して本能的な違和感を覚えるようになる。料理でも、仕事でも、人でも、そして言葉でも。
あの映画館も、あのレストランも、もうないでしょう。けれど、スクリーンの暗がりと、皿の上の衝撃の味は、いまも私の中に生きています。もしかしたら、人生の方向性は、あのとき、すでに定まっていたのかもしれません。
***